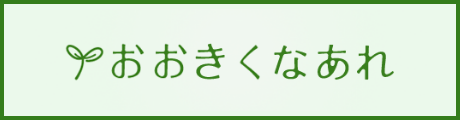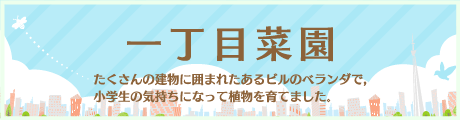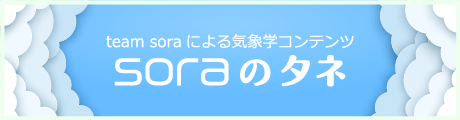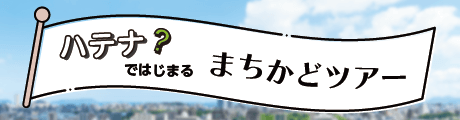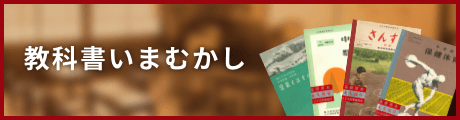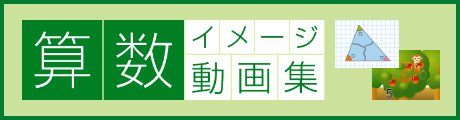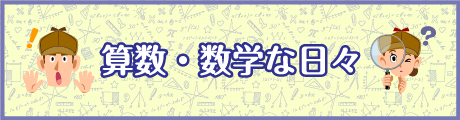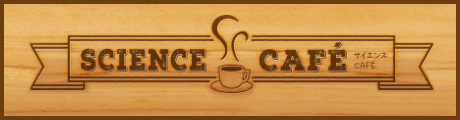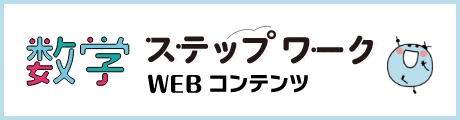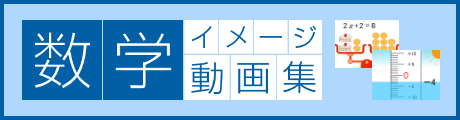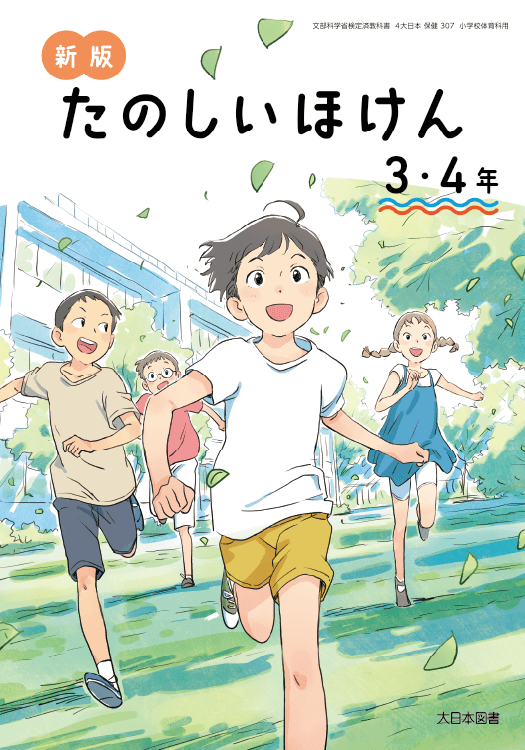小学校保健 よくある質問
-
-
Q.
教科書の折り込みは、どのように活用したらいいですか?
-
A.
導入の活動「つかもう」を行う際に下部を隠すことができます。
また、活動のヒントや情報カードとしても使えます。
-
-
-
Q.
教科書の付録には、どのようなものがありますか?
-
A.
現代的な課題として、性の多様性、SDGsなどを取り上げています。
また、感染症について大きく扱い、SNSや、がんについての資料なども豊富に用意しました。
-
-
-
Q.
知識の習得を子供が確認することはできますか?
-
A.
ウェブコンテンツに、各学習項目ごとの穴埋め問題を用意しています。
単元の終わりには、学習を振り返り、思考したことを文章に表現できるようにしています。
-
-
-
Q.
この教科書は、保健の授業以外でも活用できますか?
-
A.
小学校の保健は、健康教育・安全教育として、総合的な学習の時間や道徳の時間にも活用できます。
さらに、家庭での生活習慣の改善や、地域での安全確認など、学校以外でも活用できるようにしています。
-