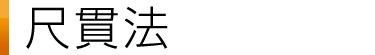
江戸時代の日本では,長さの単位に尺,質量の単位に貫を基本の単位とした単位系「尺貫法」が使われていました。
明治時代,1885年に国際的な単位の統一を目的としたメートル条約に加盟し,1891年に度量衡法が公布されたのを機に,メートル法(長さの単位にメートル $\text{m}$,質量の単位にキログラム $\text{kg}$ を基準とした単位系)が普及していきました。
1951年の計量法によって,尺貫法を取引や証明に使うことが禁止されましたが,いくつかの単位は今も身のまわりで目にすることがあります。
明治時代,1885年に国際的な単位の統一を目的としたメートル条約に加盟し,1891年に度量衡法が公布されたのを機に,メートル法(長さの単位にメートル $\text{m}$,質量の単位にキログラム $\text{kg}$ を基準とした単位系)が普及していきました。
1951年の計量法によって,尺貫法を取引や証明に使うことが禁止されましたが,いくつかの単位は今も身のまわりで目にすることがあります。
-
尺貫法の長さの単位
-
$1$ 里(り) $=$ $36$ 町 $=$ $3.9273\text{ km}$ $1$ 町(ちょう) $=$ $60$ 間 $=$ $109.09\text{ m}$ $1$ 間(けん) $=$ $6$ 尺 $=$ $1.8182\text{ m}$ $1$ 尺(しゃく) $=$ $\dfrac{1}{3.3}\text{ m}$ $=$ $30.303\text{ cm}$ $1$ 寸(すん) $=$ $\dfrac{1}{10}$ 尺 $=$ $3.0303\text{ cm}$ $1$ 分(ぶ) $=$ $\dfrac{1}{10}$ 寸 $=$ $3.0303\text{ mm}$
-
尺貫法の面積の単位
-
$1$ 町(ちょう) $=$ $10$ 反 $=$ $9917.4\text{ m}^2$ $1$ 反(たん) $=$ $10$ 畝 $=$ $991.74\text{ m}^2$ $1$ 畝(せ) $=$ $30$ 坪 $=$ $99.174\text{ m}^2$ $1$ 坪(つぼ) $=$ $1$ 平方間 $=$ $3.3058\text{ m}^2$
-
尺貫法の体積の単位
-
$1$ 石(こく) $=$ $10$ 斗 $=$ $180.39\text{ L}$ $=$ $180 390\text{ cm}^3$ $1$ 斗(と) $=$ $10$ 升 $=$ $18.039\text{ L}$ $=$ $18 039\text{ cm}^3$ $1$ 升(しょう) $=$ $\dfrac{2401}{1331}\text{ L}$ $=$ $1.8039\text{ L}$ $1$ 合(ごう) $=$ $\dfrac{1}{10}$ 升 $=$ $180.39\text{ mL}$
-
尺貫法の質量の単位
-
$1$ 貫(かん) $=$ $100$ 両 $=$ $3.75\text{ kg}$ $1$ 斤(きん) $=$ $16$ 両 $=$ $600\text{ g}$ $1$ 両(りょう) $=$ $10$ 匁 $=$ $37.5\text{ g}$ $1$ 匁(もんめ) $=$ $3.75\text{ g}$
-
単位の換算
-
空欄に数値入力することで、単位を換算することができます。
尺 $=$ $\text{m}$ 坪 $=$ $\text{m}^2$ 升 $=$ $\text{L}$ 貫 $=$ $\text{kg}$
