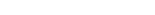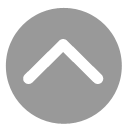現在,NHKの連続テレビ小説「つばさ」が放映されています。
マスター![]() は,まだ1度も見ていないのですが… その舞台は川越です。
は,まだ1度も見ていないのですが… その舞台は川越です。

川越と言えば小江戸,蔵造りの白壁がイメージされますね。

駅に貼られた「つばさ」のポスターを見ていて,ふと,かつて読んだ『名栗川少年記』を思い出しました。
その本の中に「…このあたりの山には、ところどころに石灰岩が露出していて、その石灰岩を原料にして、はやくから石灰の生産がさかんであった。古くは慶長の昔、日本の各地に築城がさかんになったころから、明治30年頃まで、日本の石灰の主産地であった…」とありました。
このあたりの山というのは,埼玉と東京の境の成木(青梅市)のことで,慶長というのは豊臣秀吉の時代です。
ここで作った石灰は,八王子を通って各地に運ばれたので「八王子石灰」と呼ばれ,大阪城をはじめ,京都の二条城,名古屋城,そして江戸城のあの美しい白壁に用いられました。
さて,ここで問題です。
お城や土蔵の白壁に塗られているものは,何でしょうか?
【予想】
- (ア)漆喰(しっ くい)
- (イ)コンクリート
- (ウ)石膏(せっ こう)
答えは,(ア)漆喰です。
(イ)コンクリートは,石灰石(炭酸カルシウム),粘土,珪石,酸化鉄,石膏などを原料としたもので,速乾性があり硬くて丈夫です。
(ウ)石膏は,硫酸カルシウムという物質です。水で溶かすと液状になり,すぐ固まるので美術の型取りに使ったりします。また,硬いけれどもろいので骨折したときのギプスとしても知られています。
もろくて大丈夫なの?
あんまり丈夫で,外すときにハンマーで叩き割らないといけなかったら,くっついた骨がまた折れちゃいますよ
漆喰の原料は,石灰石オンリーです。ほどよい硬さで,耐熱性,保温性,吸湿性に優れています。
江戸時代の密集した町は,火事が多かったので,耐熱性に優れる漆喰づくりの蔵がはやったのは納得ですね。
マスターの少年時代,蔵づくりの友人の家に行くと,夏は涼しく冬は暖かかったことを思い出します。