2乗すると負の数になる数!?
16世紀,イタリアの数学者カルダノ(1501〜1576)は,方程式の解法について研究しました。カルダノは,自身の著書の中で次のような問題を紹介しています。
\begin{eqnarray} \left\{ \begin{array}{l} x + y = 10 &\cdots \text{①}\\ xy = 42 &\cdots \text{②}\\ \end{array} \right. \end{eqnarray}
①を$y$について解いて②に代入すると,$x$についての2次方程式 $x^2−10x+40=0$ ができます。解の公式を使ってこの2次方程式の解を求めると,次のようになります。
$x = \dfrac{10 \pm \sqrt{-60}}{2}$
この解を見て,ふしぎに思ったことはありませんか。解にふくまれる $\sqrt{-60}$ は,「2乗して−60になる数」を表しています。しかし,みなさんは,2乗して負になる数はないと学習しています。
つまり,私たちがこれまでに学習した数の範囲では,この方程式の解を表すことができないのです。
カルダノは,3次方程式の解の公式を導く途中で,上のような2次方程式が出てくることを発見
しました。そして,「2乗して負になる数」を新しい数として導入する必要があると考えたのです。
このような数は「虚数」と呼ばれ,$\sqrt{-1}$ を $i$ という記号で表します。当初,虚数は数学者たちに認められませんでしたが,ドイツの数学者ガウス(1777〜1855)の研究などを経て認められるようになりました。
現在では,宇宙の誕生の研究など,最先端の研究にも使われています。
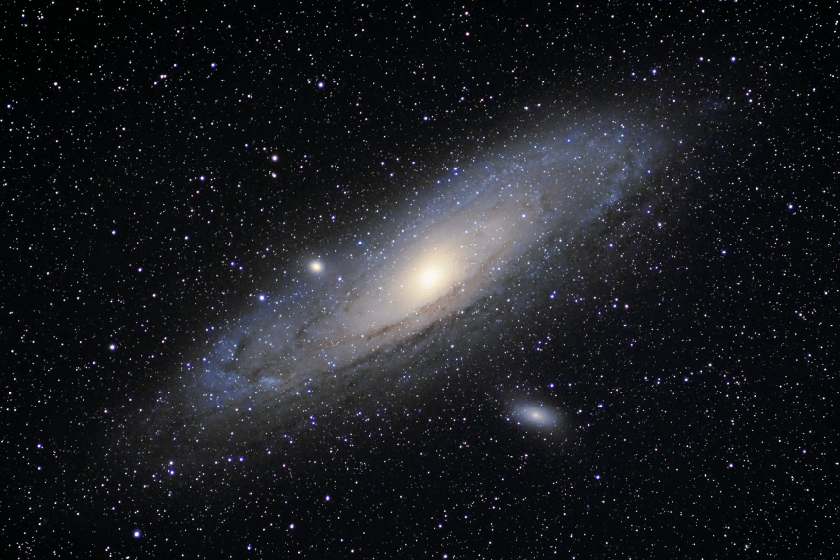
これまでに学習してきた方程式をふり返ってみると,1次方程式は,負の数や分数を使うことで解を表すことができました。2次方程式は,$x^2=2$ のようなときに,解を整数や分数で表せなくなりますが,数の範囲を平方根にまでひろげれば,$\pm \sqrt{2}$ と表すことができました。このように,新しい数を認め,数の範囲をひろげることで,解ける方程式の範囲もひろげることができるのです。
